DSPを多用してデジタル臭いのだろうか
10ヘルツ以下から20000ヘルツ以上までフラットは、力のない・活きの悪い音になってしまう。マリンバの様に共鳴管を並べれば、いくらでも、f特性はフラットに見える様に、市販のスピーカーシステムは、 バスレフを始め、 この原理から脱していない、ユニットの背圧を何かで減衰させても同じだ。
立ち上がりの鋭い単発のパルス波(大太鼓とシンバルのユニゾン)の再生はどうだろう、マルチウェイ・ホーンでは、どの様な動作になっているのだろう、
ホーン動作の説明プログラム(C言語コンパイラー付属ライブラリーが必要)
ダイアフラムで加速された空気の粒子の祖密波は音道を伝わり広がっていく、連続したサインウェーブで有れば、ダイアフラムもホーンロードを受けて、振幅も少なくて済むことは理解できるが、パルス波での動作は別だろう、DSPを使ったチャンネルディバイダーが有限の時間軸で級数展開して、まともに波形合成をしてくれるのだろうか。
鋸波をマイクで拾いながら計測をしてタイムアライメントを調整してみると、実測より時間が長くなる傾向だ、ホーンのど部の音速は開放部分より遅くなっているのだろうか、それとも、ホーンロードによって空気のムービングマスがダイァフラム に負荷となっているのだから、慣性が大きく、立ち上がりに時間がかかるのと同等なのだろうか、有限要素法解析システムプログラムを使って解析するのも一つの手だ(有限要素法のソフトは個人で手を出せる値段ではない、リースの手もあるが、生まれかわった時に興味が有ったらやってみたい) 。
DF-35のDSPのプログラムをいじってみたいところだが、今後、実験と計測・試聴によって、更に解明していきたい
2011年3月加筆
実測より時間軸が遅れ方向へズレている事に関しては、DSPプログラムに起因することが判明、DF-55等では、その事を明記し、解決方法を講じているらしい。
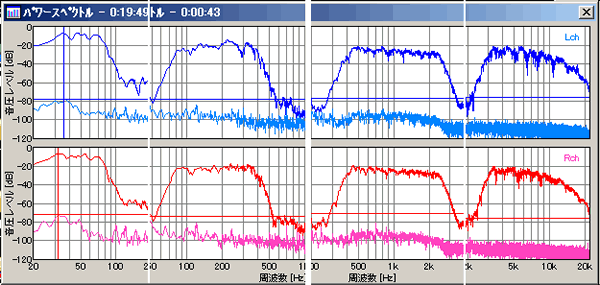
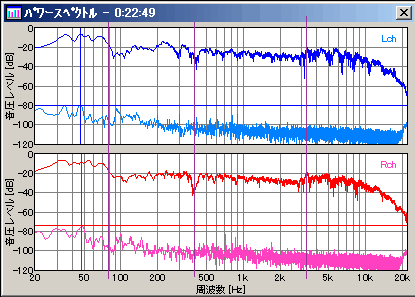
4ウエイそれぞれのスィープ特性、と総合特性、カットオフは80・400・3150としてみた、
2004年12月現在では、5ウェイとなって2オクターブずつ受け持っているいるので、周波数特性はあまり意味を成さなくなった。
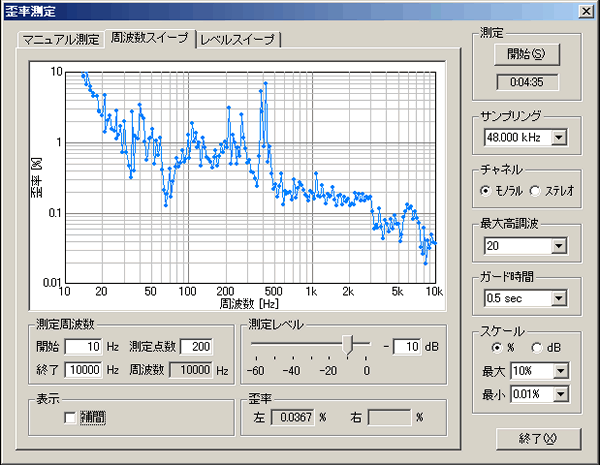
予想通り、低音の歪みは大きいし、高音の歪みは小さい、
しかし、これは高調波を20次までとしてあっても、高音の高調波はマイク等の性能上、測定し切れていないと思う。