ホーンスピーカー組上用クレーンの製作
クレーンがほぼ完成、仮組調整段階に移った。
SG-3880BLを着脱してテストした。
バランス的にクリティカルな条件で動かしてみた。
既に製作に掛かってから、3か月ほど要しているが、これも、理想の音を追求する大事な作業の一部だ。各ヒンジやベアリングにバックラッシュは無い、重要な強度部品のストラットも付いて、乗って遊んでも剛性が高いのを感じる事が出来る、設計通り出来ている証だ。
中低音以上のドライバーが載り、バランスがと捕れたまま自由に動かす事が出来るだけでなく、スロート部分のネジ着脱の為に、ドライバーをローラーの上で回転させることもできる仕組みだ。
SG-146組立用のハンガーを使用するときは又変身する事ができる、これらが無いと、重量物で構成された、ホーンスピーカーのフィックスは無理だ。
最近の予定のない日は、
午前、CAD・インターネットからのデーターで図面引き。
午後、工作室にこもる、旋盤作業などは10分の1ミリ(職人用語で"コンマ1")単位・デジタルノギスの分解能までの精度で仕上げられる様になった。
SG-146LD-4・3本パラ接続の雄姿。
左上のコントロールボタンは上部をドラッグして移動可能・早送り印で自動再生。比較する物が無いと大きさの実感が湧かないが、この写真でも、やはり表現できない。低音ホーンの進捗状況はここをクリック。
1.大きい数値制御工作機械マシンニングセンターのスケジュールを縫って、オーダーの運びとなり、統合スロート主要部分が今月中に納入される。
2.形状が複雑なため、何回も設計をやり直し、最適化を狙った。
3.2DのCADでは、無理があり、やはり、3D-CADに手を出さざるを得なかった、このソフト面白くてついつい、はまってしまった。 (左の図がその一部)
4.更に、10分の1の模型の切削もやった、これには、フライス作業の割出盤にとどまらず、傾斜テーブルまで必要だった。
5.これらのドライバーは、既に購入済みの、Accuphase PX-650 6chデジタル・パワーアンプで各々をドライブする。十分な空気の負荷と低歪を狙って、ダィアフラム合計面積を約1/3に絞ってあるのだが、各ドライバーが、その逆起電力(反作用)で相互に影響しあうのを防ぐ為だ。従って、このスロートアダプターからの音はアンプ入力以降の忠実度を1本の場合に比べ約1.7倍、有効にするはずだ。

トランジェントの良い超低歪な低音を遥かなダイナミックレンジで40Hzまでホーンでフラットにする決意が出来た。やはり超低音は46センチ・ダイアトーンに任せるのには変わりない、再生可能音圧としてはバランスは取れないままになるが、これらのホーンスピーカーと、張り合ったら、音圧で家が疲労破壊を起こしてしまうだろうから、この位が現実の上限だろう。低音ドライバーユニット3本パラ/チャンネル使用し、特殊な絞り方をして、改装低音コンクリートホーンに付ける。ホーン長も6メートル弱に伸ばして、略ストレートホーンにする、家の裏をぶち抜くので、家の裏にブロック小屋を増設しなければならない。手始めに、ホーンの部分破壊用として、土木工事用強力ハンマードリルを購入した、
これから数ヶ月かけて、トンネル堀を敢行するのだ。同時進行で、新型ホーンのCAD設計も進めている。
(2007年8月4日時点でまだ設計段階から脱していない、修行の日々だ。)
色々な、ソフトを聴いていて、最近疑問が湧いてきた、それは写真に例えられると思う。フォーカスや構図が、はっきり判らない、どうしてなのか、やはり自分で録音してみて、検証したくなった。CD等で聴いているのは、位相の正確さなど程遠い音なのだ、水面に波が広がるような音が欲しい。HDD-Recording16bit44.1Khz録音でも、十分、なのだが、録音にマルチマイクは必要悪、複数の伝送経路を、2チャンネルに纏めるから無理があるのだろう。G-0sによるマスタークロック、
Core2-Quad・i-RAM-Drive・RAID-5
MOTU-Traveler-24bit/192Khz
Multi track recording
Newmann AKG microphone・・・・
昔の38cm/2Tr録音時代から見たら、
夢のようなスペックだ。
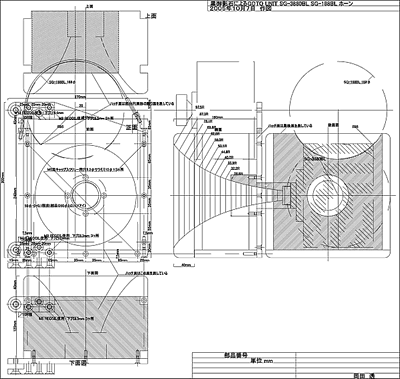
CAD図面完成、発注。GOTO UNIT SG-3880BL、
GOTO UNIT SG-188BLの導入だ、
まもなくJBLとTADを換装する。ドライバーユニットが理想的なのだから、ホーンも同様に、黒御影石と超超ジュラルミンを使用してリジッドで理論的に突き詰める。ストーンテクノ、ナガタ工業、とCADデーターをやり取りして、打ち合わせ完了、発注。
このコンポーネントだけで60㎏を越える重さになるはずだ、
2005年9月18日
画面クリックで、領収した超超ジュラルミン部分の説明が始まる。
妥協を排除したホーンはどんな音になるのかご期待あれ・・・・。

ナハトムジーク鷹松社長とAssistance Designの稲葉取締が試聴に来られた。
GEM-TS208を持ってこられて、24日まで、試聴した、やはりTADのホーントゥイーターより美しい、弦楽合奏もボリゥムいっぱいで安心して聞ける、能率は18dB程も低いので、これを安心して鳴らすにはA-20Vではチョット心配だ、金属打楽器が活躍する曲ではVUが勢い良く0dB近くまで振っている、しかし確かに音質は良い。
左の写真は左チャンネル、マウスオーバーで右チャンネル、クリックでクローズアップと計測例がご覧戴ける。

Esoteric P-01 D-01試聴
ナハトムジーク鷹松社長のはからいでEsoteric安斉さんと我が家に持ち上げて、試聴。
2004年12月16日
Serial No.20020
Esoteric P-01 D-01到着
ラックに収まらない、存在感が強い、そのうち慣れるだろう、アナログで受けざるを得ないのだが、十分満足している、DVD-AUDIOへのバージョンアップも期待している。
当初VUK-P-0sの出番が無くなってしまった、と思ったが、聞き込むとCDはP-0s、
SACDはP-01、と言うところに落ち着いた。理論的に納得できないが、暗示にかけられているのだろうか、SACDもCDも、結局、聞き直してしまう、
つい、つい、中身を確かめた。

コンデンサーマイク>EDIROL DA-2496>AudioServer。ソフトはYoshimasa Electronics IncのRealtime Analyzerでマイクの校正も出来て、色々なパラメーターが観測できる。
デジタルフィルターをそれぞれハイパスフィルターに設定して、単独にONとしながら、パルスを入力しシンクロスコープでマイク入力を観察し、タイムアライメントを調整する。
人間の耳だけでは調整できない
領域だ、5ウェイではあるが、ダブル・ウーファーの各々のカットオフとディレイを調整して5.1ウェイとでも言おうか、詳しくは企業秘密としたい。
パルスの立ち上がり位置がセンチ単位で、リアルタイムの設定が完了する。 これにより、例えば、金属打楽器のアタック音は、まるで直接、頭を叩かれている様なトランジェントの鋭い音になった。

カーソルを置くとアンプラック、ハイパーサインレギュレーター電源ユニット 、Accuphase DF-35等が見える、このアンプラック後方に低音ドライバーユニットの一部が覗いている。

ゴトウユニット後藤社長他3名、自ら来られてSG5880BL装着、5ウェイになった不思議な音だ、能率が極端に良いのにアンプのホワイトノイズはJBLやTADより、聴感上8dbは低く他のレンジにも多大な影響を与えるのは、ベリリュウムダイァフラムや強力なアルニコ・パーメンジュール磁気回路に依る為だろうか、トランジェントが高くインピーダンスが入力信号の種類により変化するのだろうか、このドライバーのダイアフラムはバックキャビティー側からウーファーの背圧をまともに受けているが大音響にもびくともしない、ノウハウが詰まっているドライバーだ。その音は、長時間、聞いていても実に心地よい、やはりゴトウユニットに換装せざるを得ないのだろうか・・・。
クリックで特注スロートの制作
千葉県、茂原市の無藤様宅のGOTO UNIT4ウェイ・システムを聞かせていただいた。
まだ、雑誌にも紹介されていない、建物ごとの、大がかりなシステムで、40代のオーディオマニアとしては珍しく。
お持ちの機器機材類も完成品を金に飽かせて集めているのではなく、この方の技術の変遷が読みとれる、素晴らしい物ばかりだった、
中でも、私が一番興味を持ったのは、問題のコンクリートホーンにダブルのSG-146スペシャル(未だ世界にここにしかない物)、
このドライバーユニットは、実物を見てみるとすごい迫力だ、
まだ未完成だったが、その音の実力の片鱗をかいま見ることが出来た。

菊池 様の素晴らしいシステム
埼玉県、菊池様宅のGOTO UNIT最高級ユニット使用4ウェイ・システムを聞かせていただいた。{下写真}
マルチアンプの構成は我がシステムと似ていて、やはりAccuphase DC-330・DF-35・A-20V・・だが、音が出てきた一発目からトランジェントの素晴らしさ、周辺の空気の確実なドライブ力(アンプの出力が無理なく音圧に変換されている)が判る、素晴らしいシステムだった。
いったい、オーディオ世界の何人の方が、この様な音を知っているのか、「オーディオのプロ達はこの音を思い知るべきだ。」「何故、有名評論家は本物のホーンシステムを取り上げないのか・・・まあ一般的ではないことは事実だが。」「この様なホーンシステムは日本の宝で、外国の超高価なスピーカーは基本技術的には日本の後追い。」「日本は、優秀な技術の蓄積のシステムが欠けている、勿体ない事だ。」と思った。
又、「これらは菊池様の長いオーディオ歴の凝縮・・・」と理解できた。
この音を参考にすると、やはりホーンは狭帯域で2オクターブが限度、今後我がシステムには低音ドライバーを変更、等で、中高音を更に追加し、5ウェイにする決心が出来た。